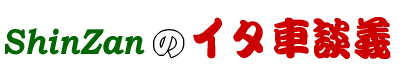
特別編「ShinZanイタリアの道路について考える(3度目のイタリア)」
イタリアに3回行ったのだが、外国へ観光に行く目的として、良い風景や、美味しい食事、人とのふれあいなど、非日常な状況を楽しむ、ということになるのだろう。
しかし、自称「メカばか」として、今回のイタリアの旅では、技術的観点から、イタリアという国の形をよく見てみたいと思っていた。特に、自動車・モーターサイクル・自転車などが好きな者として、なぜイタリアの機械はあんな風なんだろうと考えた時、唯一これら乗り物と接しているところ、つまり道路環境に適応して、進化したのだろうと想像するに至った。
ここでは、観光だと皆普段あまり気にしていない、道路の形などに関して、日本との環境の違いについて考えてみたい。
まずは、道路標識から。
日本でおなじみの道路標識も多いが、見たことのない標識や意味の違う標識もあったりする。
特に案内標識など、パッと見て判りやすい絵で表示されたものも多く、さすがに地続きの大陸なのだなという感じがする。

洞窟の観光地を示す看板。色も特徴あるが、言葉で説明するより、絵で表示されたものが多いが、これがとても重要。

パーキングメーターのところの看板など、国際的に共通のマークも多い

パーキングの標識。
奥に見える止まれの標識は日本では逆三角だがイタリアでは八角形。奥に進入禁止のマークがあるが、イメージが似ている。

補助標識も文字で無く絵で描かれているものが多い。
下の赤丸標識は、イタリア政府のホームページでも注意喚起されている、「ZTL」標識。要は車両乗り入れ禁止地区(Zona Traffico Limitato)で、日本で言うと通行止め標識に該当する。日本では赤丸の中に赤×が表示されるが、ヨーロツパでは×がなく、日本の習慣に慣れた人だと間違えやすい。ちなみに、この例だと補助標識として、6.5t以上のトラックとバスの絵が描かれていて、日本でいう大型車通行止めになるが、日本ではトラックの絵が描いてある場合の区切りは8tが標準的なので、注意が必要となる(まあ、外国へ行って大型車を運転する人はそれなりに学習しているとは思うが)

高速道路。やっぱり絵が多い。上り坂注意など、主の標識より補助標識が大きいのが面白い。なお、上の標識は日本でもあるが「その他の危険」標識だけれど、地が白色となっている。この地が黄色の場合、「その他の危険(臨時)」となり、事故多発注意などで仮設される場合がある。

駐車違反は10分でレッカーに持って行かれるよという意味かな?

路面標示が区画線を横切って書かれているのが、意図的なのかやむを得ずなのか?

もう1枚、外側線の部分にランブルストリップ(音の出る区画線:車線逸脱などの注意喚起用)が見える。これは日本でもよく見る。

カーブの視線誘導は数が多く、矢羽根も判りやすい

電光掲示板だか、日本では見ることのない、大型のF柱(というか右側通行のため、逆Fか)、日本なら門型柱だろう。

心なしか左が下がっているような・・しかし耐震基準の差にもよるのだろう。文字の左には絵が2パターン表示できる。

絵が2パターン表示されていたもの。絵の部分がフルカラー仕様になっている。さすがに片側4車線道路では門型柱。

車線減少が判りやすい。片側3車線だが、片持ち式

ここは片側2車線だが門型柱の電光掲示板。しかし支柱は細い

違う構造の門型電光掲示板。柱はやはり細い。前後の標識も腕が長く、支柱も根元が細いし。よく折れないものだ。

門型の標識。日本でよく見るトラスや円柱構造で無く、角材によるものがやはり多いようだ。外観はとてもシンプルに見える。
中央部が下がっているような気もするが・・

これも門型。柱はやはり細いが、それでもイタリアではしっかりしている方だと思う。イメージは片持ち式をつなぎあわせた感じ。部材が共通なのか?

空港へ行く途中で見た標識。板が壊れているが直していない。また、標識の上部に照明装置のようなものが付いている。ちなみに日本では、内照式やカウンタービーム方式が主流。

電光掲示板と道路標識が遠近混在しているが、配置がいいのか、重ならず、どれもよく見える(SOSの看板のみ敢えて配置を無視しているのか?)。

行き先までの距離でなく、所要時間表示(分表示)がされている。Tシステムもどこかにあるのだろう。下を見るとアウトストラーダの透過文字表示がおしゃれというか、かっこいい。
支柱はここでも片側4車線では門型のトラス式。
なお、イタリアには日本でいうオービスのような、自動速度測定装置があり(Tutorと言うらしい)、速度を常時監視されているらしい。イタリア政府観光局のHPの記載を見ると、どうも、日本で言うTシステムとNシステムを連携させたようなシステムらしく、10kmから25km間隔くらいで設置されたカメラでナンバーを読み取り、区間の平均速度が違反していれば、ナンバーを元に使用者を割り出し罰金を課す、ということのようだ。

片側4車線道路でも標識は片持ちなのがすごい。風荷重とか大丈夫なんだろうか。もっとも先端の方は面積少なくしているようだが。

ここでは区画線に注目。引き方が結構いいかげんで笑える。日本なら引き直しになるくらいの出来映え。

工事現場。「速度落とせ」の文字でなく、スピード表示が数字なのが大陸風。しかも車線の左右に表示しているのは、視認性が良く親切

車線規制。すりつけ距離は短いが、遠くから発見しやすい。工事現場で速度落とせといっても100km/hなのが、さすがアウトストラーダ。通常の制限速度は130km/h

右へのすりつけ。看板の風対策もあまり考慮されていない。日本なら脚のところにウェイト付けたり、土嚢で固定しているだろう。
80km/h制限の下にあるトラックと乗用車が描かれた標識は「追い越し禁止」標識

橋の地覆部分が剥離しているのを叩いて落としているのか?。これが車の上に落ちてきたらと思うとぞっとする

サービスエリアだが、ここはまだよく日本でも見るスタイル

空荷のためか、タイヤを1軸浮かせている。日本で走っているトラックでもたまに見かける。長距離を走るのだろうフルトレーラ車。

今回僕たちが乗ったバス。中央部にはドアやトイレもある。メーカーはゼトラ。ドイツのダイムラー傘下、エボバスのカールケスボーラーが製造するバスのブランド。過去に日本にも数台が輸入されたというが、見たことがない。

バスの天井には非常口。水没した際に有効そう。

トンネル照明はLED化され、しかも黄色LEDが多い。日本よりLED化は進んでいるかも。灯具の吊り下げ方も独特。

テレパスシステムのゲート。要はETCだが、日本よりずっと以前から実用化されていた。
見てのとおり、ゲートのバーは常時開いている。利用者を信用しているのだろう、というか、カメラでナンバー監視されているから逃げようもないのだろうが。
ちなみに現在、自動ナンバー読み取りによる通行料金徴収システム「フリーフロー」の導入が進められているようで、それが本格的に動き出せば、料金所自体が不要になる。要はTutorシステムとテレパスシステムを統合化したようなものだろうが、便利になる反面、監視社会の拡大という話にもなるのだろう。こういう話になると、AIをはじめ、革新技術というものが、本当に人間の幸せに繋がるのだろうかという話がまたぞろ出てきかねない。

セルフのガススタの看板だが、軽油が上でガソリンが下。しかもガソリンは1種類のみ。イタリアには「プレミアム」もあるのだが、あまり流通していないようだ。というのも、日本ではレギュラーのオクタン価が89以上に対し、イタリアでは95。日本でのプレミアム(ハイオク)が96以上だから、イタリアのレギュラーが日本のハイオクとほぼ同じと見ていい。イタリアはガソリンが高いと言われるが、そういう事情もあると知れば判りやすい。
ちょっと難しい話も出てきたので、ちょっと息抜きに足下を見てみることにしたい。
足下といえば路面。ヨーロッパに多くあって、日本にあまりないものの代表と言えば、石畳の路面。

ポンペイの歩道。石畳だが扇形のデザインが入っている。

アルベロベッロの歩道石畳。石の部材が大きい。長いのや短いのがランダムに敷き詰められているのが面白い

ナポリの石畳。扇形に並べられている。石の隙間が多く、自転車などには厳しい。

ナポリの石畳。やっぱり扇形に並んでいる。たまたまパトカーが写ってしまっているが、街中ではほんとに多くのパトカーを見る。

ナポリ。歩道も扇形。

ローマの車道石畳。直列的な並べ方

ミラノ。路面電車の部分のみ石畳。

これもミラノの石畳。大ブロックの石畳が車道でも使われている。
しかし、前2回の時より、石畳が少なくて、アスファルト舗装のところが多くなったような気が・・以前なら石工さんがあちこちの歩道などで、石畳の補修作業しているのを見たが、今回は見なかったし。後継者不足なのか、コストが合わなくなったのか?

ナポリ。イタリアの工事現場ではタワークレーンがよく使われている。しかしながら、日本ではブームがジブタイプなのが主流だが、イタリアを含め、ヨーロッパでは写真のような水平ブームが多い。

再び違う日に乗ったバス。今日はどこ製のバスかと思いきや、

スウェーデンのスカニア製バスでした。グリフィンのマークが特徴。といっても会社はドイツ・フォルクスワーゲンの子会社となっている。
スカニアのバスは日本でも2階建てバスや連節バスで、たまに見かける。

ごついアルミホイールにコンチネンタルのタイヤ

カプリ島。ベンツのミニバス。道が狭いので大型バスは走ることができない。逆に、日本に輸入すれば使い易いサイズと思うが。

これもカプリ島。日産やいすゞのミニバスも居た。しかし日本では見ないモデル。日本でも売ればいいのに。
路面は大ブロックの石畳(滑り止め加工入り)

こちらもカプリ島のミニバス。崖っぷちの狭いワインディングロードをガンガン飛ばす飛ばす

なおイタリアは連日40℃超えで、高速道路でも陽炎が見えたり。アメリカを思わせる風景。

ローマ。ゴルフカートだが、普通に街中に居るのがまず不思議。しかし、そもそもこの駐め方はいかがなものか。

フィレンツェ。自転車専用道。イタリアでは、歩行者が居ると車は止まるが、自転車は止まらなくて、事故が多いらしい

フィレンツェのシェア電気自動車。社会実験をやっているのか?

フィレンツェの裏通り。意外ときれいな感じ

フィレンツェのシェア自転車置き場。後方のご婦人は暑さのためか雨傘を差している。こんな人がけっこうたくさん居た。

フィレンツェ。雨が少ないためか、路面はテカテカしている。スリッピーな感じ。

自転車専用道だが、縁石でしっかり区切られている。しかしすごいのは、自転車レーンには自動車が一切停まっていない。自転車の走りを尊重していることが習慣づけられているのだろう。これを見るに付け、日本の自転車レーンの状況が情けない(開口部にキングポストが立ててあったり、隙間から自転車レーンや歩道にまで乗り上げて駐車している不届き者がいたり)。

ゴミ箱周辺はとてもきれい。

バス停。ひとけがすくない

土留め壁は、自然石のブロックでできた補強土壁か。けっこうお金かけているんじゃないだろうか。

向こう側の橋の橋脚が特徴的(柱が細い)。やはり地震などの荷重に対する基準が違うのだろう。

メストレ(ベネチア)のテレパスシステム。駐車場も高速道路と同一システムで使えるようだ。日本もこんな感じになると便利なのだが・・

一番右の車線だが、真ん中になにかレールのようなものが。と、左側奥には電車のようなものが走っている。これはまさか・・
そう、トランスロールと言われる、ゴムタイヤトラム。要は路面電車なのだが、見方によっては連節式トロリーバスか。

このトランスロール、線路が1本(案内軌条と言われる)。なにか、すぐ脱線しそうな気も。ちなみに、このトランスロール、かつて大阪に実験線があって、試験運転していたらしいが、導入する自治体等もなく、売り込みに失敗したらしい(ちなみに、元々はフランス産)。

トンネルに設置された信号機。矢印表示で判りやすい。トンネル坑口表示にも注目。反射式視線誘導がこれでもかと付けられている上、坑口に真っ直ぐにぶつからないよう、斜めにすりつけるように緩衝壁のようなものが設置されている。もしぶつかった場合でも生存率を上げるための工夫であり、こういう面では先進的な設備。

トンネルの中だが、換気用のジェットファンが6台見える。しかしその下にはスリットのような板が配置してあり、これはひょっとするとサッカルド効果を得るための装置なのかもしれない。
トンネル照明も灯具が非常に細かく設置されていて、グレアが少なくとても均一に見える。日本も見習ってもらいたい。

電気の鉄塔も1基づつ、構造が違って面白い。

サービスエリアだが、道路の上に売店や休憩施設などがあり、土地の有効活用がされている。日本ではこんな構造のところ見たことない。

サービスエリアの進入レーン。ガススタはAgipだ。パッと見、入りにくそうだが、スピードを落とさせるためのしくみなのか?ABSのブレーキ痕が見える。

また橋の上のサービスエリア。第一、8車線道路で上下線合併タイプのサービスエリアなんて日本にあったかな?
ちなみに、左側の管制塔のような建物も気になる。道路用の管制塔なのか?

アンダーパス。速度規制標識が道路センターにある。やはり左ハンドル車が多く、ドライバーから見やすい側に付けているのだろうか。もしくはコスト縮減のため、設置箇所をセンターにまとめているだけなのか・・いずれにしても合理的ではある。

信号機と道路標識が一体化していて、かく信号機は車線毎に着いている。視認性・判別性向上という点での徹底した設計はイタリア人の完璧主義にも通じるものがある。

ミラノ。青信号がレーン専用かつ矢印で判りやすい。
ちなみに、交差点というと、イタリアではけっこう、「ラウンドアバウト交差点」が多くて、信号機自体が付いていないところも多い。このラウンドアバウト交差点、直線道路においてはシケインの役目を果たし、速度超過を防ぐという効果もあることから、日本でも試験的に導入されてはいるが、なかなか普及していない。信号で停まって待つより何時でも交差点を通過できるというメリットを好む人が多いのだろう。

住宅街のひとコマ。何か日本でもありそうな雰囲気で、ほっとする。でもよく見るとプランターの付け方など、工夫している。

再びテレパスシステム。高速道路のいろいろなゲート。やはり絵で表示されていて判りやすい。有人ゲートもまだ多いようだ。

テレパスシステムとカード専用ゲート。通過速度が30km/hだ。(日本のETCは20km/h以下)

とてもカラフルな電波鉄塔。宇宙船みたい。

ミラノ。信号機が林立。信号機の配置が縦型。日本で縦型配置は積雪地に多いが、ミラノも北部ゆえ雪は多いのだろうか。

ミラノ。ビルの上の鉄塔が針金細工のよう。

ミラノ。路面電車が走っていたが、客がほとんど乗っていない。廃線にならないよね。

ミラノの自転車専用レーン。排水溝のフタまでちゃんと自転車対策しているのは、さすが自転車大国。日本の自転車道作っている人たちに見せてやりたい。

車道かと思うくらい立派な自転車レーン。交差点でもこのとおり真っ直ぐ。日本で自転車レーンの設計している人が、いかに車優先の考えに囚われているのかが判る。

街中でも普通に目立つタワークレーン。しかしクラシカルな雰囲気があり、古い街並みとの違和感があまり感じない。

子ども注意の看板だが、遅刻しそうで走って出てきそうな雰囲気がよく判る。日本では、歩いてる絵だし。

地下鉄の入口。上屋がなく、不思議な雰囲気。
とまあ、あっちこっち話が飛んでしまったが、イタリアの道路や街の形というものを紹介した。
住んでる人が違えば、環境も違ってくる。それをただ漠然と、きれいな景色だなと思って見るのもいいが、今回は「ん?なんでこんなことになってるのかな」と、その理由を想像してみるのも楽しいと思って、よく見てきた。
しかし、これを見るに付け、日本の道路事情の遅れていることよ、と痛感した。
やっぱり、イタリアはすごいし面白いや。
トップページへ戻る イタ車談義のトップへ